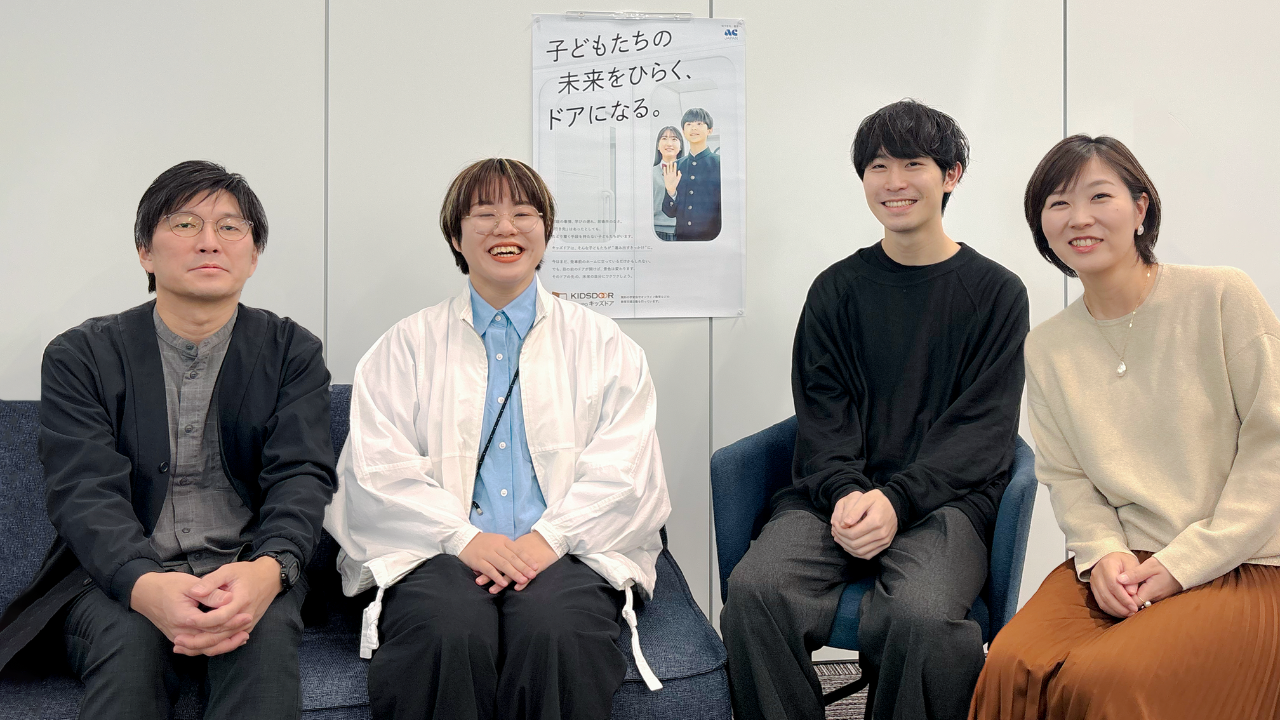インタビュー
不登校
子どもの貧困
教育格差
体験格差・IT格差
英語学習は格差が表れやすい ── 英語の学習支援最前線
「English Drive」(イングリッシュドライブ)は2016年に誕生した英語特化型の学習会だ。キッズドアの自主事業として規模を拡大し、現在は主に3つの拠点(東京都中央区・足立区・港区)における対面教室と、全国から生徒がアクセスする完全オンライン型教室を展開している。
英語学習支援の最前線で活動する、English Drive事業責任者 平井に話を聞いた。
※内容は取材当時(2024年7月時点)のものでプライバシー保護のため一部加工・編集

2024年4月開所した「ラーニングラボすみだ」に出張してEnglish Driveを開催している平井
平井 祐子(ひらい ゆうこ)
English Driveの事業責任者。洋楽を通じて英語に興味を持ち、英語に関わる仕事を目指すようになる。海外でインターンシップ等でキャリアを積み、帰国後は大手の英会話スクールでマネジメント職を経験。2021年6月入職。
格差が表れやすい英語教育
━ 経済的理由で英語を学べない人は、どこで学べるのだろうか?
英語に携わるキャリアを一貫して歩んできた平井がキッズドアに入職したのは、英語の学習支援を念頭に置いてのことだろうか?
「English Driveの担当をしているのでそう思われるかもしれませんが、社会貢献がしたいと思ったからです。営利活動をする民間企業で長年働いてきたので、そろそろ大変な状況にいる人に必要な支援を届ける仕事をしたいと思うようになり、キッズドアに出会いました」
実は、平井には前職で気になっていたことがあった。
「当たり前のことですが、英会話スクールでは費用を払って申し込んだ人にしかサービスを提供できません。ですから、本当は英語を学びたいのに、お金がないから通えない人が多いことが気になっていました」
せっかく学びたいと思っているのに、この人達はどこで学べるのだろうか? 諦めてしまっているのだろうか? そんな問いがいつも頭にあったと平井は言う。
━ 英語学習には投資が必要
グローバル化が進む時代、英語力はますます重要視されている。2020年度から小学校で英語教育が必修となったこともその証だ。教育業界大手企業の調査によると、英会話は小学生の習い事ランキングで常に上位にランクインしている。
「経済的に余裕のある家庭では、多くの子どもが英会話スクールに通っています。安いスクールもありますが、子ども達がしっかり英語を学べるスクールの月謝は高い! 英語を学ばなくても日本では生活に困らないため、困窮家庭では子どもに英語を学ばせることが贅沢と見なされ、結果的に優先順位が低くなってしまいます」
こうして、経済的困窮が子どもから英語学習の機会を遠ざけ、教育格差につながっていく。
「最近は、高校受験や大学受験で有利になると言われる英検も検定料が大幅に値上がり、気軽に何度も受験できなくなっています。さらに2024年度から新しい問題形式に変わるので、新形式の対策をするには最新の参考書や問題集も必要です」
英検3級の受験料の推移を例にとると、2014年度は3,200円、2019年度は4,900円、そして2024年度は6,900円と値上がりしている。食費を切り詰めた生活を送っている困窮家庭にとって、英検への挑戦は大きな負担となる(※)。
※キッズドアの姉妹団体「認定NPO法人キッズドア基金」では「英検奨学金」を支給している。

貧困世帯の子ども達にも英語教育を
━ 生徒のニーズに応えた先駆的取り組み
English Driveの対象生徒は(1)ひとり親世帯 (2)生活保護世帯 (3)児童扶養手当受給世帯 (4)就学援助受給世帯 (5)子どもが多い困窮世帯(多子世帯)のいずれかに該当する、英語を学びたい中高生だ(※)。該当項目が多い世帯の生徒が優先される。
※中央区の対面型教室のみ小学5~6年生も対象。オンライン型教室は高校生のみが対象。
「対面教室では週に1回2時間、オンライン型教室では週に1回1時間、完全無料で開催しています。生徒は学校の宿題や定期テスト対策、英会話や英検対策など、ボランティアとマンツーマンで勉強しています」
他の学習会と同様に、English Driveも多くのボランティアのサポートに支えられている。
「ボランティアは、英語が好きな社会人やリタイアされた方が多く、大学生や外国人の方もいらっしゃいます。オンライン型教室の場合は、海外在住のボランティアも参加しているんですよ。海外に住みながら日本に貢献ができると喜んでいる声もあり、良いプラットフォームになっています」
English Driveを利用する生徒は5〜6年通うケースが多いので、ボランティアとの交流も必然的に長期に渡る。
━ 支援の現場で感じる教育格差
平井は、生徒達の英語力についてどのように感じているのだろうか?
「英語に対して苦手意識を持つ子が明らかに多いと感じます。学び直しが必要な生徒も多く、なかには中1の基礎から学び直さないといけない高校生もいます」
English Driveに来る生徒がなぜ英語に苦手意識を持つようになったのか、個別の事情は分からないが……と前置きをした上で、平井は二つの理由を挙げた。
「一つ目は、経済的な事情で英会話スクールや参考書、問題集など、子どもの英語教育に投資できなかったことです。
二つ目は、家庭で英語を学ぶ環境が整っていないことです。多くの生徒がひとり親世帯や多子世帯の子どもです。そのため、勉強を見る人がいなかったり、学習スペースが確保できないなど、英語に限らず落ち着いて学習に集中できる条件が揃っていないと感じます」
English Driveはこれらをカバーし、生徒一人ひとりに合わせた英語教育を提供する。

学習支援とロールモデル
━ 勉強が楽しくなってきた
オンライン型教室では引きこもりがちな生徒も参加しているという。
「小学生の頃から不登校気味という高校生が、家から出ることなくオンラインで勉強できるので毎週出席しています。おかげで、勉強が楽しくなってきたと話していました。また、ボランティアと話す経験を重ねたことで、久しぶりに学校に行った時に、あまり話したことがない人とも会話ができたと言っていました」
オンライン型教室の展開により、様々な事情で対面教室に来られない生徒にも学習の機会を届けることが可能になって、とても良かったと平井は言う。
━ 大人が親身に話を聞いてくれるのが嬉しい
ボランティアと話すことで生徒が変わっていったケースは他にもある。
「English Driveに来たばかりの頃は中学生で、ちょっと英語に興味がある程度の生徒がいました。
その子は主に金融業界で働くボランティアとマンツーマンで勉強をしていました。長い期間関わるうちに親密な話をするようになり、勉強のことだけでなく、どうやって現在の職業にたどり着いたのか、困り事をどう乗り越えてきたのかなど、深い話を聞くことで次第に意識が変わっていったのです。成績がすごく伸びて、高校生のうちに英検準1級に合格することができました」
親や学校の先生以外の大人が親身になって話を聞いてくれるのを、とても嬉しいと感じているようだったと平井は振り返る。
「その生徒は高校を卒業して進学しましたが、ここで出会ったボランティアのような大人になりたいと言って、今は中学生に勉強を教えるアルバイトをしているそうです」
ロールモデルとの交流を通じて、生徒が自身の未来に対する視野を大きく変えたケースだ。
-1.png)
高尾山ハイキング
.png)
アート施設訪問
持続可能な支援を提供したい
━ 英語を使った体験学習も提供
平井は入職して4年目に入った。ここまでの活動についてどう思っているのだろうか?
「入職したのはコロナ禍で活動が制限される時期でしたが、その後は学習支援はもちろん体験学習についても、質・量ともに良い支援が提供できるよう努力してきました。生徒達から多くのポジティブな反応があり、形になってきた手応えを感じています」
English Driveは英語を使った体験学習にも力をいれていて、対面教室の生徒を日帰り遠足に連れていったり、オンライン型教室の生徒を地方から東京に招いて英語合宿を行ったりしている。
「生徒達はただでさえ家庭が経済的に大変な上に、勉強においてもハンデを負っています。さらに、周りの友達は色々な所に出掛けているけれど、自分はどこにも行けていない体験格差があることにも気付いているので、少しでも多くの体験活動を提供したいと思っています」
━ 学習支援を通じて「生きる力」の土台を作る
英語を使った体験学習は英会話を実践する場となり、人々との関わりや体験を通じて、教室の学びとは違った成長のきっかけとなる。
「親子間の会話が全くないという生徒が、東京の英語合宿に参加してくれたことがありました。家では全く喋らない子で、家出をしてしまうこともあったそうです。
その生徒は英語合宿から帰ると、『こんな友達ができた』『こんなすごい所に行った』と、楽しそうに喋ってくれたそうです。すごく久しぶりに会話ができて良かったとお母さんから喜びの連絡をもらいました」
良い成績を取ったり、いい大学に進学することは良いことではあるが、それよりも大切なことがあると平井は言う。
「前向きに自分で考える力、そして困った時には他人の力を借りる力 —— これらすべてを含めた『生きる力』を身につけることが大切だと思います。その土台を作る場を提供する役割が学習支援にはあるのだと思います」
━ この支援をどこまで継続できるのだろうか?
もっと支援が集まったらどんなことをしてみたいか、平井に聞いてみるとこんな答えが返ってきた。
「まずは、この学習会をどこまでキープできるかが気になります。新たに何かを追加したいというよりも、現在行っている英語の学習支援や体験学習を持続できるようにしたいです」
5~6年通う生徒が多いEnglish Driveだからこそ、途中で支援内容の変更を余儀なくされることなく安定して運営したいという。
「生徒がEnglish Driveに通ううちに、できなかったことができるようになったり自信をつけていく姿を間近で見れることが、私のモチベーションになっています」
今年の夏も生徒達に充実した体験学習を届けるために、平井は準備を進めている。
【シリーズインタビュー記事】
- #04 英語学習は格差が表れやすい
- #03 準貧困層は行政の支援の網からこぼれ落ちている
- #02 受講生を増やしても、全国に支援はまだ届いていない
- #01 僕は、今の時代こそ居場所が必要だと思う
キッズドアでは最新情報をメールマガジンで配信しています。ぜひご登録ください。