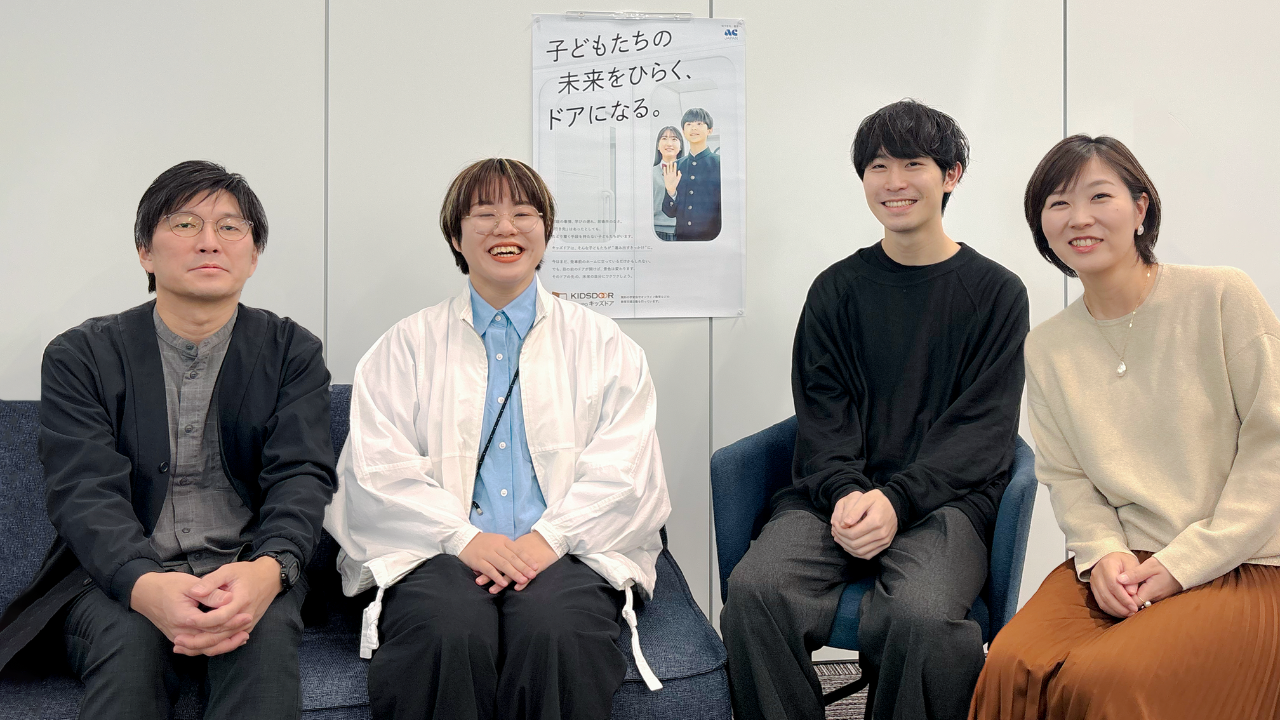インタビュー
子どもの貧困
教育格差
ひとり親世帯の貧困
理解が得られにくい今こそ必要な高校生世代への支援 ── 高校生支援最前線
2024年10月、キッズドア初の関西拠点となる無料学習支援事業「キッズ・ポートたるみ」が開設された。主に小学生を対象としたこの事業に続き、11月には、低所得家庭の高校生が難関大学を目指すための無料学習支援事業「キッズドア下村龍馬塾」がスタートした。
両事業の責任者を務める松田に、高校生支援の現状と課題について話を聞いた。
※内容は取材当時(2024年11月時点)のものでプライバシー保護のため一部加工・編集

高校生世代の支援に関わるキッズドア職員と(中央が松田)
松田 麻里(まつだ まり)
キッズドア初の関西拠点「キッズ・ポートたるみ」と「キッズドア下村龍馬塾 垂水校」の事業責任者。教員を目指していたが、学校の外で子ども達を支える道を選びたいと思い、新卒で地元九州のNPOに入職。その後、教育への知識と経験を深めるため大学進学予備校で勤務。2021年6月、念願だったキッズドアに入職。
先生が対応しきれない子ども達を支える道
松田は、大学で教職課程を履修し、教員になることを目指していた。教育実習で初めて高校の教壇に立った時、どこか上の空の生徒や心ここにあらずな生徒に目が向いてしまったという。
「気になる子に、休み時間や放課後に『今日は授業に集中できていなかったけど、どうしたん?』と声をかけると、『実は色々と大変な状況で…』なんて話を聞くこともありました。先生はこういう部分をフォローしきれない現実があるんだなと気づきました」
もちろん先生も問題に気づいている。ただ、個別に向き合ったり、その背景を深く探ったりするには、忙しすぎて時間が取れないのだ。
「教育は、学校の先生、家庭、さらにソーシャルワーカーやNPOのような子どもに関わるセクションが包括的に連携することで、子どもにとって最善のサポートができると思います。自分はどのフィールドで働きたいのか考えたとき、学校の中では限界があるので、学校の外で子ども達を支える道を選びたいと思いました」
そうして松田は、新卒でNPOというフィールドを選んだ。その後、進学予備校で教育の知識と経験を積み、かねてより働きたいと願っていたキッズドアに入職した。
どの子にも『変わるという未来』がある
━ 「変わる瞬間」を信じて寄り添う日々
以前から、高校生世代の支援を希望してきた松田。キッズドアに入職すると、貧困世帯や生活困窮世帯、または何らかの困難を抱える高校生の拠点を担当し、様々なケースを見てきた。
「例えば、中学までずっと不登校だった生徒が高校に入学したものの、やっぱりうまくいかないという子も中にはいます。でも私は、どの子も変わるという未来がわかるので、楽しみでしかないんです」
最初の生徒・保護者との三者面談は、様々な理由によって保護者が生徒を連れて来られず、何度もキャンセルになることもある。
「やっと面談に来てくれても、最初は目も合わせてくれないんです。でも1か月くらい経つと、気づけば拠点によく顔を出していて、あれ?ボランティアの大学生や社会人のスタッフとボードゲームしてるじゃん!となっていくんですよね」
まずは、“ここは安心していられる場所だ” と感じられることが何より大切。だからこそ、日々の信頼関係の積み重ねが重要で、それが次の成長を生み出すと松田は考えている。
━ 大学生との出会いが未来への興味を灯す
さらに2~3ヶ月もすると、生徒の口から ”少し勉強してみようかな?” という言葉が出るようになる。その変化の背景には、ロールモデルとの出会いがある。
「それまで自分の周りにいなかった大学生や社会人と話していると、『この人達、普段は何をしているんだろう?』と自然と興味を持つようになるんです。そして、『大学って何?』『どんなところなの?』と言い始めた時が、あっ来た来た!と待っていた瞬間です」
しかし、変化はまだ始まりに過ぎない。
「大学の話をすると、最初は『さらに4年も学校に行きたくない』って言われるんです。そこで、『大学卒業だとこういうメリットがあるよ』『短大や専門学校もあるんだよ』と話を重ねていくと、『それなら行けるかも』と前向きになり、いつの間にか学校のテストで良い点を取っていることもあります」
高校卒業後の未来を描けなかった生徒が、最終的に大学を受験するケースも多い。
「様々な事情で、卒業後の世界を知らなかったり諦めてしまっている生徒達に、いろいろな選択肢や可能性を提示して、自分で選べる幅を広げることができる。それが、この仕事をしていて一番良かったと思う瞬間です」

生徒とスタッフがゲームする様子を見守る松田(中央奥)
教育格差は情報・場所・出会いにもある
━ 受験の情報格差
松田が都内の高校生向け拠点を担当していたときから感じているもの。それは、教育格差の存在。教育格差は学習面だけではなく、情報、場所、そして出会いにも大きな差があるという。
「情報の中でも特に差が大きいのが受験の情報です。今の大学受験は、一般入試以外にも多くの形式があり、近年その仕組みがどんどん複雑化しています。大学独自の入試方式も多様化していて、学校では気軽に質問しづらい状況です。また、保護者からも “自分の頃とは全く違うので何もサポートできない” という声をよく聞きます」
例えば、ある私立大学の経済学部だけを見ても、一般選抜(令和7年度)では、A個別方式、N全学統一方式、C共通テスト利用方式など合計7種類の選抜方法がある。さらに、学校推薦型選抜や総合型選抜も加わり、仕組みは一層複雑化している。
受験情報を知らない、理解していないことは、生徒達の選択肢を狭め、合格の可能性にも影響を及ぼす。
「通知表の成績が良ければ、推薦入試で面接だけで合格できる場合もあります。それを知らないことで受験のチャンスを逃すのは、本当にもったいないことです」
そのため、松田は受験のサポートを通じて、生徒達が知らずに不利益を被らないようにしたいと考えている。そして、もっと多くのチャンスを掴んでほしいと願っている。
━ 勉強する場所と、人との出会いの格差
勉強場所の有無もまた、大きな差の一つである。
「塾には、自習室のように勉強だけに集中できる静かな空間があります。でも、それがない生徒達にとっては大きなハードルです。学校の図書室も利用時間が限られていますし、遅くまで開いている図書館に行くには交通費がかかります。カフェはお金が必要ですし、長居すると店員さんに気を遣ってしまいます」
結果として、勉強する場所が家しかなくなってしまう。
「でも、家だとどうしてもだらけてしまったり、集中できないことが多いんです。さらに厳しい経済状況の家庭では、節電のためエアコンが使えなかったり、そもそも自分だけの机や部屋が無いこともあります」
環境の違いが結果に大きく影響する。松田はそう感じている。
そして、出会う人の差。
「塾に通う生徒達は、塾の先生や大学生チューターにいつでも相談できます。それが彼らの仕事なので、受験に必要な情報も豊富です。受験期は精神的に不安定になりやすい時期なので、応援してくれる人がそばにいることが本当に大切だと思います」
さらに、一緒に切磋琢磨できる仲間の存在も重要だという。
「よく聞くのは、塾の自習室のように自分と同じく受験に挑んでいる仲間が周りにいる、そうした環境でないとモチベーションを維持するのが難しいという話です。私が普段関わる生徒達は経済的に厳しく、勉強する場所もなければ出会える大人も限られています」
環境だけでなく、支援してくれる人や仲間の有無もまた、結果に大きな影響を与える要素だ。


『キッズドア下村龍馬塾 垂水校』の内観
困窮世帯の高校生の苦悩
━ 進学の夢を遮る経済的な壁
キッズドアは、2011年から困窮世帯の高校生を支援している。高校が義務教育ではないため、高校生への支援を行うNPOや自治体は少なく、その支援は圧倒的に不足している。
そのため、大学進学を目指す困窮世帯の高校生達からは、毎年キッズドアに切実な声が寄せられる。
- 本当にお金がなくて、受験料も、交通費や宿泊費も出せません。模試代すら厳しいです
- 学校では、一人一人丁寧に進路面談をしてくれるわけではないので、どう受験の戦略を立てていいのか全然わからないです
- 受験方式が多すぎて、この経済状況の中、どれを選べばいいのか分かりません
- 塾に通えないので家でしか勉強できず、ずっと一人でやっているとしんどくなります
- 寂しいです
- 相談できる人がいません
- 経済的な理由で浪人できないので、絶対合格できる大学までランクを下げざるを得ません
松田はこうした現状に立ち向かうため、キッズドア初の関西拠点 “キッズドア下村龍馬塾 垂水校” の立ち上げに取り組んでいる。低所得家庭の高校生や既卒生を支援する無料学習支援事業だ。現在はその生徒募集活動に奔走している。
「ありがたいことに、生徒募集を始めて2週間で、定員の20名が埋まりそうな勢いです。本当にこの事業は必要だったんだなと感じています。難関大学を目指せる学力があるし、将来こうなりたいという夢も抱いている。でも経済的な理由で諦めなければならないなんて、本当に悔しいです。どうにかしてあげたいと思っています」
努力だけでは越えられない経済的な壁。“キッズドア下村龍馬塾” では、そうした高校生達に必要な支援を届け、未来ある若者の可能性を広げようとしている。
━ 理解や共感が得られにくい高校生世代への支援
高校生世代への支援が十分に行き届かない理由。それは、この世代の課題が社会で理解されにくいからだ。松田はその背景に、義務教育ではないこと、そして時代の違いがあると指摘する。
「義務教育が小中学校までということもあり、高校生以上への支援は『本人や家庭の努力次第』と考えられがちです。少し前までは『お金がないなら大学進学なんて贅沢だ』という風潮もありました。それと同じ感覚で、高校生への支援も『必要以上のこと』と思われている部分があるのだと思います。高校生世代への支援はこども支援の最後の砦です。ここを逃すともう支援できるタイミングは無くなります」
義務教育の範囲を超えることで、支援の手が薄くなる。この構造が、多くの高校生を取り残している。
もう一つの理由は、今の高校生を取り巻く現状が、支援者世代の経験とは大きく異なることだ。
「保護者の方からよく聞くのは、『自分の時代と今の受験や進路の状況が全く違うから、サポートのしようがない』という声です。例えば受験制度の複雑化や進学に伴う費用の増加、デジタル環境など、今の高校生が直面している課題は、かつての常識が通用しない部分が多いです。また、小中学生と違って高校生世代が抱える課題は複合的で困難性が高いケースが多いです。そのため、支援者側の誰もが簡単に対応できるわけではないというハードルの高さがあります。そうした現状を、社会全体で共有するのが難しいのだと思います」
理解や共感が得られにくい高校生世代の支援。その状況の中で、松田は一貫して生徒達に “学ぶことや知ることは一生の武器になる“ と伝えているという。
「その子自身のせいではない困難を抱えている高校生達にとって、必要な情報を事前に得ることが将来を決めるうえで重要な要素となります。情報がなければ、取捨選択すらできません。学び続ける姿勢を大切にすること、そして貪欲に知識や情報を求めること。今の時代において、それが彼らの未来を切り開くひとつの鍵であると同時に、一生の武器になると思っています」
高校生世代が貧困の連鎖を断ち切り、抱える困難を乗り越え、未来ある社会の一員として力強く羽ばたいていくために、社会全体の理解と支援が ”今” 求められている。
ーーーーーーーーーー
【シリーズインタビュー記事】
- #08 理解が得られにくい今こそ必要な高校生世代への支援
- #07 子ども達は様々な大人との出会いで成長する
- #06 継続的に活動することが子どものためになる
- #05 子どもの居場所には地域の課題を解決する可能性がある
- #04 英語学習は格差が表れやすい
- #03 準貧困層は行政の支援の網からこぼれ落ちている
- #02 受講生を増やしても、全国に支援はまだ届いていない
- #01 僕は、今の時代こそ居場所が必要だと思う
キッズドアでは最新情報をメールマガジンで配信しています。ぜひご登録ください。